相続税申告は、人生で何度も経験するものではなく、非常に専門的で複雑な手続きです。税理士に依頼することで負担は軽減されますが、「税理士なら誰でも相続税に詳しい」わけではないのが実情です。税理士の知見や経験次第で、納税額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
この記事では、相続税申告で失敗しないための税理士選びについて、以下の点から網羅的に解説します。
- 解説すること:相続税申告に本当に強い税理士の「具体的な探し方(ポータルサイト等)」「専門性の見極め方(チェック方法)」「依頼を決定する際の最終確認ポイント」
- 明確になること:広告や料金の安さに惑わされず、ご自身の財産状況やご家族にとって最適な、信頼できる税理士を選ぶための「具体的な基準」が明確になります。
- 読み終わった後:不安なく無料相談に臨み、自信を持って「この人だ」と思える専門家(パートナー)を見つけるための一歩を踏み出せます。
大切な財産を適切に守り、円満な相続を実現するために、専門家選びの「軸」をしっかり持ちましょう。
相続税申告に強い税理士を選ぶ10のポイント
相続税申告は、専門的な知識と経験が求められる複雑な手続きです。税理士に依頼することで、申告手続きの負担軽減だけでなく、適切な財産評価や特例の適用による節税効果も期待できます。
しかし、税理士なら誰でも良いわけではありません。相続税申告に強い税理士を選ぶことが重要です。ここでは、相続税申告に強い税理士を選ぶための10のポイントを解説します。
相続税申告の実績と経験
相続税申告は、所得税や法人税の申告とは異なり、財産評価や特例の適用など、独自の専門知識と経験が必要です。そのため、税理士を選ぶ際には、相続税申告の実績が豊富かどうかを確認することが非常に重要です。
- 年間申告件数:相続税申告を年間で何件程度扱っているかは、経験の豊富さを測る一つの指標となります。多くの案件を手掛けている税理士は、様々なケースに対応するノウハウを蓄積している可能性が高いです。具体的な件数をウェブサイトで公開している事務所もありますし、直接問い合わせて確認することも有効です。
- 経験年数:相続税専門、あるいは相続税案件を中心に扱っている年数も確認しましょう。長年の経験は、複雑な案件や予期せぬ問題への対応力につながります。特に10年以上の経験を持つ税理士は、税制改正の変遷も理解しており、より深い知識を持っていることが期待できます。
- 過去の取扱事例:特に、ご自身の状況(例えば、土地の評価が複雑、非上場株式がある、相続人が多いなど)に類似した案件の取り扱い経験があるかを確認すると良いでしょう。具体的な事例への対応実績を聞くことで、その税理士の専門性や問題解決能力を推し量ることができます。
相続税申告は、税理士の経験やノウハウによって納税額が大きく変わる可能性のある分野です。ホームページやパンフレットだけでなく、無料相談などを利用して、直接税理士に実績や経験について質問し、信頼できるかどうかを見極めることが大切です。
相続税に関する専門知識
相続税申告を適切に行うためには、相続税法だけでなく、民法(相続法)や不動産評価、非上場株式評価など、幅広い専門知識が不可欠です。税理士がこれらの分野に精通しているかを確認しましょう。
- 相続関連法規の知識:相続税の計算だけでなく、遺産分割協議のアドバイスや、民法の相続規定(法定相続分、遺留分など)を踏まえた提案ができるかどうかが重要です。相続に関する知識が浅いと、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
- 財産評価のノウハウ:相続財産の中でも特に不動産(土地)や非上場株式の評価は複雑で、評価方法によって納税額が大きく変動します。国税庁の財産評価基本通達を深く理解し、現地の状況や個別の要因を適切に反映した評価ができるか、評価に必要な調査(役所調査、現地調査など)を丁寧に行うかなどがポイントです。
- 最新税制への対応力:税法は頻繁に改正されます。相続税に関する最新の税制改正の内容を常に把握し、適切に対応できる税理士であるかを確認しましょう。税理士向けの研修会への参加状況や、事務所内での勉強会の実施状況なども参考になります。
特に土地評価においては、路線価方式だけでなく、様々な補正(不整形地補正、広大地評価(現在は地積規模の大きな宅地の評価)など)や特例(小規模宅地等の特例など)を駆使できる知識と経験が求められます。
これらの専門知識は、単に資格を持っているだけでは測れません。相談時に具体的な質問を投げかけ、その回答の的確さや分かりやすさから、知識の深さや経験の豊富さを判断することが重要です。
料金体系の明確さ
相続税申告を税理士に依頼する際、費用がどのくらいかかるのかは非常に気になるところです。料金体系が不明確だと、後々トラブルになる可能性もあります。事前に料金体系が明確に提示されている税理士を選びましょう。
- 料金体系の明示:ホームページやパンフレット、または最初の相談時に、料金体系が分かりやすく説明されているかを確認しましょう。「遺産総額の〇%」といった基本的な報酬基準だけでなく、どのような場合に加算報酬が発生するのかが具体的に示されていることが望ましいです。
- 報酬の内訳:見積もりを依頼する際には、基本報酬、加算報酬(土地評価、非上場株式評価、相続人の数などによる加算)、実費(戸籍謄本取得費用、不動産登記簿謄本取得費用、交通費など)の内訳が明確に記載されているかを確認しましょう。何にどれくらいの費用がかかるのかを把握することが重要です。
- 追加料金の条件:当初の見積もりから追加料金が発生する可能性があるケース(例:当初想定していなかった財産が見つかった、遺産分割協議が難航した、税務調査の対応が必要になったなど)とその条件、料金基準が事前に説明されているかを確認しましょう。
- 複数の事務所から見積もり取得:料金だけでなく、サービス内容や対応範囲も事務所によって異なります。複数の税理士事務所から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討することをおすすめします。
ただし、単に料金が安いという理由だけで選ぶのではなく、実績や専門性、相性なども考慮して総合的に判断することが大切です。
契約を結ぶ前に、料金について疑問点があれば遠慮なく質問し、納得のいく説明を受けるようにしましょう。
コミュニケーション能力と相性
相続税申告は、税理士との間で財産状況や家族関係といったデリケートな情報も含めて、多くのやり取りが必要になります。そのため、税理士のコミュニケーション能力や、ご自身との相性も重要な選択基準となります。
- 説明の分かりやすさ:相続税に関する専門用語や複雑な手続きについて、一般の人にも理解できるよう、平易な言葉で丁寧に説明してくれるかを確認しましょう。一方的に話すのではなく、こちらの理解度を確認しながら進めてくれる税理士が望ましいです。
- 質問への対応:こちらからの質問に対して、真摯に耳を傾け、的確かつ丁寧に答えてくれるかどうかも重要です。質問しにくい雰囲気だったり、回答が曖昧だったりする場合は注意が必要です。
- 連絡の取りやすさ:申告手続きを進める中で、疑問点や確認事項が出てくることがあります。電話やメールなどで連絡が取りやすく、迅速に対応してくれるかどうかも確認しておきましょう。担当者が頻繁に変わるような事務所も、コミュニケーションが円滑に進まない可能性があるため注意が必要です。
- 人柄・相性:税理士も人ですので、どうしても相性の良し悪しはあります。無料相談などを利用して実際に税理士と会い、話しやすいか、信頼できそうか、威圧的でないかなど、人柄やフィーリングが合うかどうかを確認しましょう。相続というデリケートな問題を相談する相手として、安心して任せられると感じられるかどうかが大切です。
どんなに優秀な税理士であっても、コミュニケーションが円滑に進まなければ、満足のいく申告は難しくなります。複数の税理士と面談し、ご自身にとって最も話しやすく、信頼できると感じる税理士を選ぶことをお勧めします。
税務調査への対応力
相続税は、他の税目に比べて税務調査の対象となる割合が高いと言われています。万が一、税務調査が入った場合に、適切に対応してくれる税理士であるかどうかも重要なポイントです。
- 税務調査の経験:相続税の税務調査に対応した経験が豊富かどうかを確認しましょう。経験豊富な税理士は、調査官の指摘のポイントや交渉の進め方を熟知しており、納税者の立場に立って適切に対応してくれます。過去の税務調査の具体的な対応事例などを聞いてみるのも良いでしょう。
- 税務署との交渉力:税務調査では、財産評価の方法や解釈について、税務署と見解が異なる場合があります。そのような場合に、税法や通達、判例などに基づき、税務署に対して論理的に説明し、交渉できる能力があるかどうかが重要になります。
- 書面添付制度の活用:書面添付制度とは、税理士が申告書の作成に関して計算・整理・相談に応じた事項を記載した書面を添付する制度です。この書面が添付されていると、税務調査の前に税理士に意見聴取の機会が与えられ、調査が省略される可能性もあります。書面添付制度を積極的に活用している税理士は、申告内容に自信があり、調査対応にも慣れていると考えられます。
- 調査対応の料金:税務調査の対応は、通常の申告業務とは別に費用が発生するのが一般的です。調査対応が必要になった場合の料金体系についても、事前に確認しておくと安心です。
税務調査は精神的な負担も大きいものです。申告段階から調査を意識した丁寧な書類作成を行い、万が一調査が入った場合にも安心して任せられる税理士を選ぶことが大切です。
他の専門家との連携
相続手続きは、相続税申告だけでなく、遺産分割協議、不動産の名義変更(相続登記)、相続放棄、遺言書の執行など、多岐にわたります。これらの手続きには、税理士だけでなく、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士といった他の専門家の協力が必要になるケースが多くあります。
- 連携ネットワークの有無:相談する税理士が、これらの他の専門家とスムーズに連携できるネットワークを持っているかを確認しましょう。信頼できる各分野の専門家を紹介してもらえる体制があると、相続に関する様々な問題をワンストップで相談・解決でき、依頼者の負担が大幅に軽減されます。
- 連携実績:過去に他の専門家と連携して案件を処理した実績があるかどうかも確認ポイントです。実績があれば、各専門家との役割分担や情報共有がスムーズに行われ、手続き全体が円滑に進むことが期待できます。
- 窓口の一本化:税理士が窓口となり、必要に応じて他の専門家を手配してくれる体制であれば、依頼者はあちこちの事務所に連絡・相談する手間が省けます。特に、相続手続きに慣れていない方にとっては、大きなメリットとなります。
- 不動産鑑定士との連携:相続財産に不動産、特に評価が難しい土地が含まれる場合、不動産鑑定士による鑑定評価が必要になることがあります。税理士が信頼できる不動産鑑定士と連携しているかは、適正な財産評価を行う上で重要です。
相続手続き全体をスムーズに進めるためには、税理士が他の専門家と良好な連携関係を築いているかどうかも、重要な選択基準の一つと言えるでしょう。
相続発生「後」だけでなく「前」の相談(生前対策)
相続税申告に強い税理士は、相続が発生した「後」の申告手続きだけでなく、相続が発生する「前」の対策(生前対策)についても知識や経験が豊富です。長期的な視点で相談できる税理士を選びましょう。
- 生前対策の知識と提案力:生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与など)、生命保険の活用、不動産対策(評価額の引き下げ、共有不動産の整理など)、遺言書作成のアドバイス、事業承継対策など、様々な生前対策について、メリット・デメリットを踏まえて具体的な提案ができるかを確認しましょう。
- シミュレーション能力:現状の財産状況で相続が発生した場合の相続税額を試算(シミュレーション)し、それに基づいて具体的な対策の効果を提示できるかどうかもポイントです。シミュレーションにより、対策の必要性や効果を客観的に把握することができます。
- 長期的な視点でのアドバイス:生前対策は、一度行ったら終わりではなく、家族構成の変化や財産状況の変化、税制改正などに応じて見直しが必要になる場合があります。長期的な視点に立ち、継続的に相談・アドバイスを受けられる税理士が望ましいでしょう。
- 相続関連業務への注力度:事務所として、相続税申告だけでなく、生前対策や事業承継などの関連業務にも力を入れているかを確認しましょう。相続関連業務を専門的に扱っている事務所であれば、より質の高いサービスが期待できます。
相続は、発生してから慌てて対応するよりも、事前に準備を進めておくことで、よりスムーズに、そして有利に進められるケースが多くあります。生前対策にも強い税理士をパートナーとして選ぶことは、将来の安心につながります。
相続税申告に強い税理士を選ぶことは、円滑な相続手続きと適切な納税、そして将来の安心のために非常に重要です。今回ご紹介した7つのポイント(実績・経験、専門知識、料金体系、コミュニケーション、税務調査対応力、他士業連携、生前対策)を参考に、複数の税理士と実際に面談し、ご自身やご家族にとって最も信頼できるパートナーを見つけてください。
自宅や勤務先などから通いやすい場所にあるか
相続税申告の手続きにおいては、税理士と直接会って打ち合わせを行う機会が何度か発生するのが一般的です。例えば、初回の相談、収集した資料の確認、財産目録や遺産分割協議書(案)の説明、申告書の内容確認と押印など、重要な局面では対面でのコミュニケーションが求められることがあります。
事務所が自宅や勤務先から近い、あるいは交通の便が良い場所にあれば、これらの打ち合わせの際の移動負担が軽減されます。特に、相続手続き中は精神的にも時間的にも余裕がないことが多く、移動にかかるストレスが少ないことは大きなメリットです。また、追加の資料提出や急な相談事が発生した際にも、気軽に立ち寄りやすいという利点があります。
ただし、近年はZoomなどのWeb会議システムを活用したオンライン面談や、電話・メール、郵送でのやり取りを中心に業務を進める税理士事務所も増えています。必ずしも物理的な近さが必須ではなくなっているのも事実です。
重要なのは、「通いやすさ」と「相続税に関する専門性の高さ」を天秤にかけることです。相続税申告は税理士の知見によって納税額が大きく変わる可能性があるため、多少遠方であっても、相続税の経験が豊富で信頼できる専門家を選ぶことが最優先であるべきです。
まずは専門性を重視して候補を選び、その上で「対面での打ち合わせを希望するか」「Web面談でも問題ないか」「(遠方の場合)出張訪問は可能か」といった、ご自身の希望するコミュニケーション方法に対応可能かを確認すると良いでしょう。
無料相談に応じていているかどうか
多くの税理士事務所では、相続に関する初回の相談を無料(例:30分~60分程度)で受け付けています。この無料相談制度の有無、そしてその内容は、税理士を選ぶ上で非常に有益な判断材料となります。
税理士の専門性・人柄の確認:無料相談は、税理士の相続税に関する知識や経験の深さを直接確認できる絶好の機会です。「土地評価の方法」や「小規模宅地等の特例」など、具体的な質問を投げかけ、その回答の分かりやすさや的確さを見極めましょう。また、話しやすいか、信頼できそうかといった「相性」を確認することも重要です。
料金体系や業務範囲の確認:実際に依頼した場合の費用(見積もり)や、どのような業務をどこまでサポートしてくれるのかを具体的に聞くことができます。
比較検討:無料相談を活用すれば、複数の税理士事務所を比較検討することが可能になります。A事務所とB事務所の回答内容や対応の仕方を比べることで、ご自身にとって最適な税理士を見つけやすくなります。
「無料相談」といっても、その範囲は事務所によって異なります。
「初回のみ無料」「60分まで無料」「一般的なアドバイスのみ」など、条件を確認しておくことが大切です。また、無料相談はあくまで「見極める場」と捉え、限られた時間で聞きたいこと(特に専門性、費用、人柄)を事前に整理しておくと、より有意義な時間となるでしょう。
過去に処分等があるかどうか(懲戒処分歴の確認)
税理士は、税理士法に基づき厳格な職務遂行を求められており、もし職務に違反する行為(例:意図的な脱税相談、重大な申告漏れの見逃し、名義貸しなど)を行った場合、国税庁長官から懲戒処分を受けることがあります。
懲戒処分の種類
処分には重い順に「業務禁止」「業務停止」「戒告」の3種類があります。これらは、税理士としての信頼性や適格性に関わる重大な問題があったことを示します。
相続税申告は、依頼者の大切な財産情報を預かり、適正な申告・納税を行う極めて重要な業務です。そのパートナーとなる税理士が、過去に不正や重大な過失で懲戒処分を受けていたとしたら、安心して業務を任せることは難しいでしょう。
確認方法
税理士の懲戒処分歴は、国税庁のウェブサイトで公表されています(「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等」)。また、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」では、税理士が現在正規に登録されているか(処分により登録抹消などになっていないか)を確認することができます。
税理士を選ぶ際には、その専門性や実績だけでなく、「職業倫理に基づき誠実に業務を行ってくれるか」という信頼性の確認も不可欠です。契約を検討する前に、これらの公的情報を確認しておくことは、リスクを回避するために有効な手段と言えます。
税理士が相続税申告に知見があるかを確認・チェックする方法
相続税申告は、依頼する税理士の知見や経験によって、納税額や手続きの円滑さが大きく変わる可能性があります。経験豊富に見える税理士が、本当に相続税申告に精通しているかを見極めることは非常に重要です。
ここでは、税理士の相続税申告に関する知見の深さを確認・チェックするための具体的な5つの方法を解説します。
土地評価の具体的な方法について質問する
相続財産に土地が含まれる場合、その評価方法が相続税額に最も大きな影響を与えます。土地評価は非常に専門性が高く、税理士の知見が如実に表れる分野です。
知見を確認するには、「この土地(例えば、自宅の敷地)はどのように評価しますか?」と具体的に質問してみてください。単に「路線価に面積をかけて計算します」という回答だけでは不十分です。
本当に知見のある税理士であれば、まず「現地調査」や「役所調査」の重要性を説明するはずです。その上で、国税庁の定める財産評価基本通達に基づき、以下のような点を網羅的に確認しようとするでしょう。
- 路線価方式・倍率方式の確認:まず基本的な評価方式を確認
- 各種補正の検討:土地の形状(不整形地、間口が狭い、奥行きが長い等)、接道状況(二方路線、無道路地、セットバックの必要性等)、周辺環境(騒音、日照阻害等)に応じた評価減(各種補正)の可能性を探ります。
- 利用状況の確認:貸家建付地や貸宅地(他人に貸している土地)に該当しないか、私道として利用されている部分はないかなどを確認します。
- 特例適用の検討:小規模宅地等の特例(後述)が適用できるか、そのための要件は満たしているかを検討します。
これらの確認を怠ると、土地を過大に評価し、不要な税金を納めることになりかねません。財産評価基本通達をどれだけ深く理解し、実務で使いこなしているかが、税理士の力量を測るバロメーターとなります。
「小規模宅地等の特例」の適用可否について具体的なケースで質問する
「小規模宅地等の特例」は、相続税の節税対策として最も効果的な特例の一つです。例えば、被相続人の自宅敷地(特定居住用宅地等)であれば、一定の要件を満たせば330平方メートルまで評価額を80%減額できるため、納税額に数百万円、数千万円単位の影響を与えます。
しかし、この特例は適用要件が非常に複雑で、税理士によっても見解が分かれるケースがあります。そこで、あえて少し複雑なケースを想定して質問してみるのが有効です。
例えば、以下のような質問を投げかけてみてください。
- 「相続人は長男と次男です。長男は被相続人(父)と同居していましたが、次男は別居しています。この場合、長男が実家を相続すれば特例を使えますか?」
- 「父は亡くなる3年前に老人ホームに入所していましたが、住民票は実家に残したままでした。この場合、実家の敷地に特例は使えますか?」
- 「被相続人は二世帯住宅に住んでいました。相続人(子)の居住スペースと区分登記されている場合、特例の適用はどうなりますか?」
知見のある税理士であれば、国税庁のタックスアンサー(例:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例))などを根拠に、それぞれのケースにおける判断基準(例:生計を一にしていたか、家屋の所有者は誰か、介護の状況、建物の構造など)を明確に説明してくれるはずです。
適用可否の判断理由や、そのために必要な証拠資料(住民票の履歴、介護認定の書類、公共料金の支払い状況など)を具体的に提示できるはずです。
税務調査の経験と指摘事項について聞く
相続税は、他の税金(所得税や法人税)と比較して、税務調査の対象となる割合が高い税目です。国税庁の発表(※)によれば、実地調査の件数自体は変動しますが、調査対象となった場合、申告漏れ等の非違を指摘される割合は非常に高い水準で推移しています。(※例:令和4事務年度の相続税の調査等の状況では、実地調査の非違割合は81.9%)
したがって、税務調査への対応力は、相続税に強い税理士を見極める上で不可欠な要素です。
確認方法としては、「相続税の税務調査は、どのような点が指摘されやすいですか?」あるいは「過去にどのような税務調査の経験があり、どのように対応されましたか?」と率直に尋ねてみることです。
経験豊富な税理士であれば、具体的な指摘ポイントを即座に挙げられるはずです。
- 名義預金・名義株:被相続人のお金で、配偶者や子・孫名義で作った預金や株式(いわゆる名義財産)が、相続財産から漏れていないか。
- 生前贈与の否認:暦年贈与(年間110万円まで非課税)のつもりが、証拠不備(贈与契約書がない、本人が通帳を管理していた等)で否認され、相続財産に加算されるケース。
- 土地評価の妥当性:前述した土地評価において、減額要因の見落とし(納税者不利)だけでなく、過度な減額(税務署からの指摘対象)がなかったか。
さらに、書面添付制度(税理士法第33条の2)を積極的に活用しているかも確認ポイントです。
これは税理士が申告書の作成内容が適正であることを保証する書面を添付する制度で、税務調査の前に税理士への意見聴取が行われ、調査が省略される可能性もあります。この制度の活用状況も、税理士の自信と専門性の表れと言えます。
生前対策(節税・納税資金・分割)の提案内容を聞く
相続税申告に強い税理士は、相続が発生した「後」の申告業務だけでなく、相続が発生する「前」の生前対策にも精通しています。そこで、「将来の相続税が心配なのですが、どのような対策が考えられますか?」と質問してみてください。知見の深さを測るポイントは、節税対策、納税資金対策、遺産分割対策の3つの視点から、バランスの取れた回答が得られるかどうかです。
例えば、節税対策として「暦年贈与」だけを勧める税理士は要注意です。知見のある税理士なら、2024年(令和6年)からの税制改正(生前贈与加算が3年から7年に延長、相続時精算課税制度への基礎控除110万円創設)を踏まえ、暦年贈与と相続時精算課税制度のメリット・デメリットを比較説明するはずです。
さらに、以下のような多角的な提案ができるかが重要です。
- 納税資金対策:「節税はできても、納税する現金がない」という事態を防ぐため、生命保険の非課税枠(法定相続人の数×500万円)の活用や、所有不動産の一部売却(どの不動産を売るべきか)などを提案できるか。
- 遺産分割対策:節税ばかりを優先して、相続人間で揉め事を起こさないよう、遺言書の作成支援や、財産を分けやすい形(例:不動産共有の解消、株式の整理)にしておくことの重要性を説明できるか。
- 財産評価の引き下げ:不動産(特に土地)の評価額を下げるための対策(例:賃貸アパートの建設、いわゆる「小規模宅地等の特例」の活用を見据えた同居など)のメリットとリスク(空室リスク、借入金リスクなど)を具体的に説明できるか。
これらの提案を、相談者の家族構成や財産状況を踏まえて具体的に行える税理士は、高い専門性を持っていると言えるでしょう。
申告までの具体的なスケジュールと必要資料リストを求める
相続税申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限はタイトであり、多くの手続きを効率よく進めなければなりません。
税理士の実務経験の豊富さは、この「段取りの良さ」に表れます。初回の相談時に、「申告までに、いつ頃、何をすべきか」という具体的なスケジュール感と、「そのために必要な資料は何か」を明確に説明できるかを確認しましょう。
経験豊富な税理士であれば、以下のような流れをよどみなく説明できるはずです。
- 相続人の確定(約1〜2ヶ月): 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書の収集。
- 財産・債務の調査確定(約1〜3ヶ月):
- 金融資産: 預貯金(過去数年分の取引履歴含む)、有価証券の残高証明書(相続開始日時点)。
- 不動産: 登記簿謄本、公図、測量図、固定資産税評価証明書。
- その他: 生命保険金支払通知書、死亡退職金支払通知書。
- 債務: 借入金残高証明書、未払いの医療費・税金の領収書。
- 財産評価(約2〜4ヶ月): 特に土地評価(現地調査、役所調査含む)。
- 遺産分割協議(約3〜6ヶ月): 評価額に基づき、相続人間で分割内容を協議・決定し、遺産分割協議書を作成。
- 申告書作成・提出(〜10ヶ月): 全ての資料に基づき申告書を作成し、税務署へ提出、納税。
知見のある税理士は、単に資料リストを渡すだけでなく、「なぜその資料が必要か(例:過去の預金履歴は名義預金や生前贈与の確認のため)」「どの資料の取得に時間がかかるか(例:戸籍の遡り)」を熟知しており、効率的な収集方法や、税理士側で代行取得できる範囲を具体的に提示してくれます。この段取り力こそが、豊富な実務経験の証となります。
相談後の税理士の決め方|実際に依頼する税理士を選ぶときのポイント
相続相談を終え、複数の税理士候補の中から実際に依頼する1名を決定する段階は非常に重要です。相談時の印象や説明内容を踏まえ、以下の5つのポイントを最終的に確認し、総合的に判断することをお勧めします。
見積もり内容と料金体系の妥当性
無料相談などを通じて、複数の税理士事務所から見積もりを取得している場合、その内容を詳細に比較検討します。ここで確認すべきは、単なる金額の安さではなく、「料金体系の明確さ」と「サービス内容とのバランス」です。
相続税申告の報酬は、一般的に遺産総額に応じて設定されますが、それ以外にどのような費用が発生するのかが重要です。チェックすべき項目は以下の通りです。
- 基本報酬に含まれる業務範囲:財産評価、遺産分割協議書作成サポート、申告書作成・提出までが基本か。
- 加算報酬の有無と基準:土地評価(特に複数の土地や評価が複雑な場合)、非上場株式評価、相続人の数、申告期限までの日数などによって、どの程度の加算が発生するのかが明記されているか。
- 実費負担:戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの取得費用、不動産鑑定士への依頼費用(必要な場合)、交通費などが別途請求か、報酬に含まれるか。
- 税務調査対応の料金:申告後の税務調査の立ち会い費用は、別途発生するのが一般的です。その場合の料金基準(日当、時間制など)が示されているか。
「相続税申告 一式 〇〇万円」といった曖昧な見積もりではなく、業務内容とそれに対応する費用が具体的に記載されているかを確認しましょう。安すぎる見積もりは、必要な財産評価(特に現地調査など)を省略されるリスクがないか、逆に高すぎる見積もりは、業務内容に見合っているかを慎重に判断する必要があります。
相談時の回答(特に財産評価)の具体性と専門性
相談時に行った具体的な質問(例えば、自宅の土地評価や小規模宅地等の特例の適用可否など)に対して、どれだけ的確で専門的な回答が得られたかを思い出してください。相続税申告の質は、財産評価、特に土地評価の精度に大きく左右されます。
- 土地評価への言及:単に「路線価方式で計算します」ではなく、国税庁の財産評価基本通達に基づき、「現地調査の必要性」「役所調査(都市計画道路、上下水道など)の重要性」「不整形地補正や間口狭小補正などの各種減額要因の検討」について具体的に言及があったか。
- 特例適用の判断:「小規模宅地等の特例」など、節税効果の高い特例について、適用要件を正確に説明し、相談者のケースで適用可能か、あるいは適用するために何が必要か(例:遺産分割の方法)まで踏み込んだアドバイスがあったか。
- リスクの説明:節税対策や評価方法について、メリットだけでなく、税務調査で指摘される可能性(税務リスク)やデメリットについても、包み隠さず説明してくれたか。
専門用語を並べるだけでなく、こちらの質問の意図を汲み取り、平易な言葉で、根拠(通達や過去の事例)を示しながら具体的に回答してくれた税理士は、高い専門性と実務能力を持っていると期待できます。
担当者の人柄とコミュニケーションの相性
相続税申告は、相続開始から10ヶ月という期限までに、担当税理士と非常に密なコミュニケーションを取りながら進めていく作業です。財産内容だけでなく、家族関係といったデリケートな情報も共有する必要があります。
そのため、知識や経験が豊富であることと同時に、「この人になら安心して任せられる」と感じる人柄や相性が極めて重要になります。
- 質問のしやすさ:些細なことでも疑問点を気軽に質問できる雰囲気があるか。こちらの話を遮らず、最後まで丁寧に聞いてくれるか。
- 説明の分かりやすさ:難しい専門用語を避け、こちらの理解度に合わせて説明を尽くしてくれるか。
- レスポンスの速さ:相談時の対応や、その後の連絡(見積もり送付など)が迅速かつ丁寧であったか。レスポンスの速さは、業務遂行の誠実さや効率性と比例することが多いです。
- 威圧的でないか:専門家としての立場を一方的に押し付けるのではなく、相続人の状況や意向を尊重し、一緒に最適な申告を目指す姿勢(パートナーシップ)を感じられるか。
申告手続きの過程では、様々な判断や確認が必要となります。「この人には聞きづらい」「連絡が取りにくい」と感じる相手では、ストレスが溜まるだけでなく、重要な情報の伝達漏れにもつながりかねません。
相談時のフィーリングを大切にし、信頼関係を築けそうかを見極めてください。
申告までのスケジュール感と段取りの良さ
相続税申告には「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という厳格な期限があります。この限られた時間の中で、戸籍の収集、財産調査、財産評価、遺産分割協議、申告書作成・提出という多くのステップを完了させなければなりません。
相談時に、申告完了までの具体的なロードマップ(工程表)やスケジュール感を明確に提示してくれたかは、その税理士の経験値と段取り力を測る重要な指標です。
- 全体の流れの説明
「まずは戸籍収集」「次に財産調査」「評価が固まったら分割協議」といった、申告までの流れと、それぞれのステップで「誰が(税理士か、相続人か)」「何を」「いつまでに行うか」を具体的に説明してくれたか。 - 必要資料の提示
財産調査や評価に必要な資料リスト(預金通帳、不動産の権利証、保険証券など)を提示し、「なぜその資料が必要か(例:過去の預金履歴は名義預金の確認のため)」を説明してくれたか。 - 期限への意識
10ヶ月という期限の重要性と、特に時間がかかる作業(例:土地評価、遺産分割協議)について言及し、余裕を持ったスケジュールを提案してくれたか。
経験豊富な税理士は、過去の多くの案件から、どこに時間がかかり、どのようなトラブルが起きやすいかを熟知しています。相談の段階で、全体像を見据えた段取りを具体的に示せる税理士は、期限内に円滑かつ正確な申告を導いてくれる可能性が高いと言えます。
税務調査への対応方針と他士業連携(アフターフォロー)
相続税申告は、申告書を提出して終わりではありません。前述の通り、相続税は税務調査の対象となる割合が比較的高い税目です。また、申告と並行して、不動産の名義変更(相続登記)や、場合によっては遺産分割で揉めた際の法的手続きが必要になることもあります。
申告後の万が一の事態(税務調査)や、申告以外の関連手続き(登記、法務)にも対応できる体制が整っているかを確認しましょう。
- 税務調査への姿勢
申告書に書面添付制度(税理士法第33条の2)を適用することを標準としているか。これは、税理士が申告書の適正性を保証する書面を添付するもので、税務調査の前に税理士への意見聴取が行われるため、調査自体が省略される可能性が高まります。この制度を積極的に活用しているかは、税理士の自信と誠実さの表れです。 - 税務調査対応の経験:相談時に、税務調査の経験や、どのような点が指摘されやすいかを具体的に説明できたか。
- 他士業との連携:税理士が窓口となり、必要な専門家を紹介・連携してくれる体制(ワンストップサービス)があれば、相続手続き全体の負担が大幅に軽減されます。
申告業務そのものの専門性に加え、こうしたアフターフォローや関連業務への対応力も、最終的な決定における重要な判断材料となります。
相続税申告に強い税理士の具体的な探し方
相続税申告という専門性の高い業務を任せる税理士を探すには、いくつかの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて使い分けることが重要です。
ここでは、相続税申告に強い税理士の具体的な探し方を5つ挙げ、それぞれの特徴と活用時の注意点を専門家の視点から解説します。
税理士紹介ポータルサイト(相続専門サイト)を利用する
現在、最も一般的な探し方の一つが、インターネット上の税理士紹介ポータルサイトを活用する方法です。特に「相続専門」をうたうサイトは、相続税申告に特化した情報が集約されています。
最大の利点は「比較検討のしやすさ」です。地域(例:「東京都世田谷区」)と業務内容(例:「相続税申告」「生前対策」)で絞り込むことができ、複数の税理士事務所の概要、実績(年間申告件数など)、料金体系の目安、得意分野(例:不動産評価、事業承継)、利用者(依頼者)の口コミなどを一覧で比較できます。多くのサイトが無料相談の申し込みフォームを備えており、気軽にコンタクトを取りやすい点も特徴です。
税理士ドットコム

日本最大級の税理士紹介プラットフォームで、専任コーディネーターが要望をヒアリングし最適な税理士を完全無料で提案、面談設定までサポートするのが特徴です。
上場企業である弁護士ドットコム株式会社が運営し、税理士検索や口コミ、Q&Aなどの機能を備えて比較検討と疑問解消を並行しやすい導線になっています。確定申告期の生産性向上に向けAIによる案件紹介文生成機能を導入するなど、依頼者と税理士双方の体験を高める取り組みも進んでいます。
公式サイト: https://www.zeiri4.com
ミツモア(税理士)
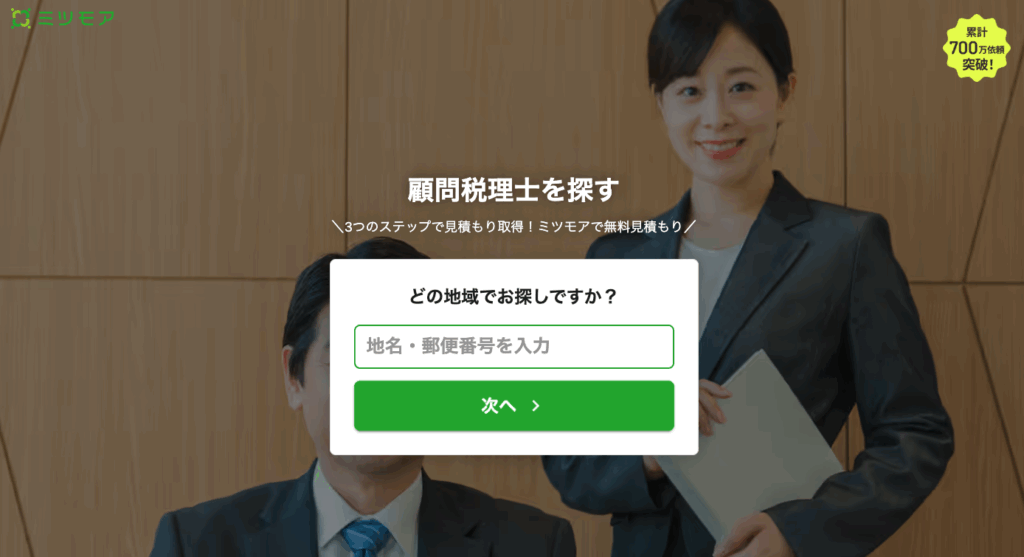
士業を含む多様なプロの見積もり比較ができるオンラインサービスで、税理士分野でも料金や口コミを見ながら地域・ニーズ適合度で候補を比較し、そのまま依頼に進めます。確定申告・顧問・相続申告など用途別にカテゴリが整理され、成約データに基づく最新の費用相場を確認できるため、初期検討段階でのコスト把握に強みがあります。
首都圏を含む各エリアで掲載が充実し、万一の際の保証制度も掲げるなど、Web完結でスピーディーに絞り込みたい場合に使いやすい総合マッチング基盤です。
公式サイト:https://meetsmore.com/
税理士紹介センタービスカス

30年の紹介実績を持つ老舗で、利用者の希望を丁寧にヒアリングしたうえで最適な税理士を全国から完全無料で紹介する体制が整っています。累計紹介件数は40万件以上(2024年実績)とされ、医療など専門分野別の特化サイトも展開することで業種や課題に応じた精度の高いマッチングが期待できます。
面談調整まで伴走し比較検討を支援する運用方針で、初めての税理士選びや乗り換え時のミスマッチ低減にも配慮された導線が特徴です。
公式サイト: https://www.all-senmonka.jp
税理士会(支部)の紹介制度や相談会を利用する
全国の税理士は、日本税理士会連合会に属し、各地域(都道府県単位)の税理士会、さらにその下の「支部」に所属しています。これらの税理士会や支部では、税理士を探している人向けの紹介制度や、無料税務相談会を運営している場合があります。
公式サイト:https://www.zeirishikensaku.jp/
税理士会という公的な団体を通じて紹介を受けるため、「正規の税理士である」という点での安心感は非常に高いです。また、地域の税務署や役所などで開催される無料相談会は、地元の税理士と直接話せる良い機会となります。地域の事情に精通した税理士に出会える可能性もあります。
税理士会の紹介制度は、必ずしも「相続税申告に強い税理士」をピンポイントで紹介してくれるとは限らない、という点に最大の注意が必要です。
紹介方法が名簿順や当番制である場合、「相続税申告の経験が少ない」税理士が紹介される可能性も十分にあります。無料相談会も同様で、担当する税理士が法人税や所得税の専門家であるケースも多いです。
税理士会を利用する場合は、「相続税申告の実績が豊富な税理士を紹介してほしい」と具体的に希望を伝える努力は必要ですが、過度な期待はせず、紹介された税理士の専門性を別途自身で確認するプロセスが必須となります。
金融機関(銀行・信託銀行・証券会社)からの紹介
被相続人が生前に取引していた銀行(特に信託銀行)や証券会社に相談し、提携している税理士を紹介してもらう方法です。
金融機関、特に信託銀行は、遺産整理業務や遺言信託、事業承継などを幅広く扱っており、富裕層の相続案件に関するノウハウを蓄積しています。そのため、提携している税理士も、相続税申告、特に金融資産や不動産評価、事業承継に関する経験が豊富である可能性が高いです。また、被相続人の口座情報など、財産(特に金融資産)の把握がスムーズに進む場合があります。
金融機関からの紹介は、あくまで「提携先」の税理士です。
依頼者が複数の候補から自由に選べるわけではなく、中立性に欠ける可能性があります。また、金融機関が提供する「遺産整理業務」などのパッケージサービスの一環として税理士が紹介される場合、その費用(紹介料や手数料)が税理士報酬に上乗せされている、あるいはパッケージ料金全体が高額になるケースも考えられます。
紹介された税理士の専門性を信頼しつつも、提示される料金が適正か、他の税理士に直接依頼した場合と比較検討する視点も必要です。
他の専門家(司法書士・弁護士)からの紹介
相続手続きを進める過程で、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合は司法書士、遺産分割協議で紛争(揉め事)が発生した場合は弁護士に依頼することになります。これらの専門家から、連携している税理士を紹介してもらう方法です。
専門家同士は、日頃の業務を通じて互いの得意分野や仕事の進め方を熟知しています。特に相続案件を多く扱っている司法書士や弁護士が「この先生なら信頼できる」と紹介する税理士は、相続税申告の実務能力が高い可能性が非常に高いです。専門家による「目利き」を経ているため、信頼性の高い紹介が期待できます。また、登記や法務と、税務申告をスムーズに連携して進められる点も大きなメリットです。
紹介元となる司法書士や弁護士自身が、相続案件(特に税務)に精通していない場合、紹介される税理士も同様に相続税の経験が豊富でない可能性があります。例えば、不動産登記がメインで相続税申告はあまり扱わない司法書士からの紹介では、最適な税理士が見つかるとは限りません。
紹介を受ける際は、紹介元の専門家がどれだけ相続案件を扱っているかも、一つの判断材料にすると良いでしょう。
インターネット検索(Google検索など)による直接検索
ポータルサイトを経由せず、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで「(地域名) 相続税 税理士」「相続 土地評価 強い」「相続税申告 実績」といったキーワードで直接検索し、税理士事務所の公式ホームページを探す方法です。
能動的に、ご自身のニーズに合わせたキーワードで探せるため、専門性の高い税理士事務所を直接見つけ出せる可能性があります。事務所の公式ホームページには、ポータルサイトよりも詳細な情報(税理士の経歴や考え方、具体的な業務実績、詳細な料金表、専門的なコラム記事など)が掲載されていることが多く、事務所の姿勢や専門性の高さを深く知ることができます。
検索結果で上位に表示される事務所が、必ずしも最も実力のある事務所とは限りません。検索順位は、広告費(リスティング広告)やSEO(検索エンジン最適化)対策の巧拙に大きく左右されます。
広告やSEOに力を入れていなくても、実直に業務を行っている優秀な税理士も多く存在します。ホームページの内容を慎重に読み解き、その事務所が本当に相続税申告に強いのか(例えば、掲載されているコラムの内容が具体的で専門的か、財産評価基本通達への言及があるかなど)を見極める必要があります。
この方法で見つけた場合も、必ず無料相談などで直接対話し、実力を確認することが重要です。
税理士選びで失敗しないための注意点5つ
相続税申告の税理士選びは、申告手続きの円滑さや納税額に大きな影響を与えます。専門知識や経験が不足している税理士に依頼してしまうと、本来納める必要のない税金を支払ったり、税務調査で指摘を受けたりするなど、深刻な「失敗」につながりかねません。
ここでは、税理士選びで失敗しないために特に注意すべき5つのポイントを、専門家の視点から解説します。
「相続税専門」の看板や広告だけを鵜呑みにしない
インターネットで検索すると、「相続税専門」や「相続税に強い」とアピールする税理士事務所が多数見つかります。しかし、この「専門」という言葉には法的な定義や基準はありません。極端な話、相続税申告の経験が年間数件であっても「相続専門」と名乗ることは可能です。
広告やホームページの「相続専門」という言葉だけを信じて依頼したところ、実際には経験が浅く、相続財産の大部分を占める土地の評価が「路線価に面積を乗じただけ」という単純な計算で終わっていたケースがあります。この場合、国税庁の定める財産評価基本通達に基づく様々な減額要因(例:不整形地、無道路地、騒音、日照阻害など)が一切考慮されず、本来よりも数百万円単位で過大な納税になってしまうリスクがあります。
「専門」という言葉だけでなく実績を必ず確認してください。
無料相談の際に、「相続税申告の年間件数」や「経験年数」を尋ねるだけでなく、「自宅の土地はどのように評価しますか?」と具体的な質問を投げかけましょう。その際、現地調査や役所調査の重要性に触れ、財産評価基本通達に基づいた複数の減額要因を検討する姿勢を見せる税理士は、信頼できる可能性が高いと言えます。
税理士なら誰でも相続税に詳しいという思い込みは危険
税理士資格は同じでも、その専門分野は医師に内科や外科があるように、大きく異なります。多くの税理士は、企業の顧問として法人税や所得税(確定申告)を主な業務としています。
被相続人が会社経営者だったため、長年お世話になっている顧問税理士にそのまま相続税申告を依頼するケースは非常に多いです。しかし、その顧問税理士が相続税申告(特に複雑な財産評価や特例の適用)に精通しているとは限りません。相続税申告は、税法だけでなく民法(相続法)の知識、そして前述の「財産評価基本通達」という特殊なルールを駆使する高度な専門性が求められるためです。結果として、経験不足から「小規模宅地等の特例」の適用要件を見誤ったり、財産評価で不利になったりする失敗が起こり得ます。
長年の付き合いがある顧問税理士であっても、まずは「相続税申告の実績が豊富か」を客観的に確認してください。もし実績が少ないようであれば、相続税申告だけを別の専門税理士に依頼する(顧問契約は継続したまま)という選択肢も積極的に検討すべきです。
相続税申告は、税理士の知見によって納税額が大きく変動する分野であることを認識することが重要です。
料金の「安さ」だけで選ばない
相続税申告の税理士報酬は自由化されており、事務所によって料金体系は様々です。当然、依頼者としては費用を抑えたいところですが、料金の「安さ」だけで税理士を選んでしまうと、深刻な失敗を招く危険性があります。
報酬の安さ(例:遺産総額の0.5%未満など、相場より極端に安い)を理由に依頼したところ、税理士がコスト削減のために、時間と手間のかかる「現地調査(土地評価のため)」や「役所調査(都市計画道路の確認など)」を省略した。その結果、本来適用できたはずの評価減(例:セットバックによる減額)が見逃され、節税できたはずの金額をはるかに上回る相続税を納めることになった。また、安価なプランでは税務調査対応が別料金(高額)であることもあります。
安すぎる報酬には、「作業が簡略化される」あるいは「必要な業務が含まれていない」リスクがあると疑うべきです。複数の事務所から見積もりを取得し、単なる総額ではなく、「基本報酬に何が含まれているか」「どのような場合に加算報酬が発生するか(例:土地評価の筆数、相続人の数)」を詳細に比較してください。
安さの理由を明確に説明でき、業務の質を担保する(例:必ず現地調査を行う)と明言する税理士を選びましょう。
無料相談時の「相性」や「違和感」を軽視しない
相続税申告は、相続開始から10ヶ月という期限内に、税理士と密に連携しながら進める必要があります。その過程では、財産内容はもちろん、家族構成や時には家族間の関係性といった、非常にデリケートな情報も共有しなければなりません。
「実績はありそうだが、相談時に少し高圧的で質問しづらい」と感じた税理士に、専門性を期待して依頼した。しかし、申告手続き中に疑問点があっても気軽に聞けず、税理士からの説明も一方的で理解が追いつかない。結果として、遺産分割の方法について相続人側の意向が十分に伝わらず、税理士主導で「税務上は楽だが、相続人の希望とは異なる」分割案で申告が進んでしまった。
税理士の専門知識や実績は当然重要ですが、それと同等以上に「コミュニケーションの取りやすさ(相性)」が重要です。無料相談の場で、こちらの話を遮らずに最後まで聞いてくれるか、専門用語を多用せず平易な言葉で説明してくれるか、質問しやすい雰囲気を作ってくれるか、といった点を厳しくチェックしてください。
どんなに優秀でも、信頼関係を築けないと感じる税理士に依頼すると、10ヶ月間大きなストレスを抱えることになります。
税理士への「丸投げ」姿勢でいない(業務の質を見極める)
相続手続きは複雑で面倒なため、「専門家である税理士にすべてお任せしたい(丸投げしたい)」と考える相続人は少なくありません。しかし、この姿勢は非常に危険です。
税理士に「すべてお任せします」と伝え、税理士側も相続人への詳細なヒアリング(特に被相続人の生前の資金の流れ)を怠った。税理士は通帳の残高だけを見て申告書を作成したが、その後の税務調査で、被相続人が管理していた「孫名義の預金(いわゆる名義預金)」や「契約書のない生前贈与」が多数発覚。これらは相続財産として申告すべきであったため、申告漏れとして多額の追徴課税(加算税・延滞税含む)を課された。
失敗を防ぐためには、相続人自身も情報提供に協力する姿勢が必要です。そして、それ以上に「税理士側が、納税者から必要な情報を引き出す努力をしているか」を見極める必要があります。
信頼できる税理士は、税務調査で指摘されやすいポイント(名義預金、生前贈与など)を熟知しているため、相続人に対し、被相続人の生前の状況について詳細なヒアリングを行います。
また、申告書の信頼性を高める「書面添付制度」の活用に積極的かどうかも、税理士の誠実性や業務の質を見極める重要な判断基準となります。
まとめ
ここまで、相続税申告に強い税理士の具体的な探し方、知見の見極め方、依頼時の最終確認ポイント、そして失敗しないための注意点を多角的に解説してきました。
税理士紹介サイトの活用や、金融機関からの紹介など、出会いの方法は様々です。しかし、どの方法で探す場合でも、最終的に重要なのは「広告や料金の安さ」ではなく、「相続税申告の実績に裏打ちされた専門性」と、「デリケートな内容を安心して相談できる信頼関係(相性)」の2点に尽きます。
特に、納税額に直結する土地評価(財産評価基本通達の習熟度)や、小規模宅地等の特例に関する質問への回答、税務調査への対応方針は、その税理士の実力を測る試金石となります。
無料相談は「依頼する場」ではなく「見極める場」です。ぜひ本記事のチェックポイントを活用し、複数の税理士と直接対話し、自信を持って任せられるパートナーを見つけてください。




